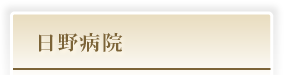今年度の診療報酬改訂の影響 -中山間地の地域医療は維持できるか -令和6年9月
今年度、大きな診療報酬 改定がありました。その結 果、多くの中小病院は厳し い経営環境に直面していま す。われわれ、現場の人間 には理解が難しい部分が多くあります。まず、職員の賃上げによ り人件費が大幅に増加しました。多くの分野で賃上げを国が推進 していることは良いことであり、それに反対するわけではありま せん。しかし、一般企業では必要に応じて価格に転嫁することで、 人件費の増加分を補うことが可能ですが、医療においては価格が 公定価格であるため、それを上げることができません。また、新 たな診療報酬改訂でも、中小病院ではそれに見合った診療報酬の 増加は期待できません。当病院でも、ここ数ヶ月の人件費の上昇 を補うほどに収入は増加していません。賃上げは全ての医療機関 に関わることなので、全ての医療機関が得ることができる診療報 酬の増額が必要です。
もう一つの例として、看護必要度の基準が非常に厳しくなって います。看護必要度とは患者さんがどの程度の看護を必要として いるか、多くの看護師を必要とするかを評価する指標です。看護 必要度によって入院基本料が変わります。これまでと同じ看護を していても、入院料が大幅に減少する可能性があります。高度急 性期病院でも、看護必要度の基準が厳しくなり、入院料が増加す る病院と減少する病院が出てきます。厚労省の意図は機能分化を より明確にすることであり、それを急性期病床の適正化と呼んで いますが、これが本当に適正化と言えるのでしょうか。急性期病 床の縮小は、特に高齢者救急の受け入れ先がなくなり、高齢化が 進んでいる地域の医療が崩壊する可能性があります。これは、高 齢者にはこの程度の医療で済ませるべきだという暗黙の意図があ るのかもしれません。また、地域ごとの特殊事情を考慮すること もありません。都会のように様々な機能を持つ病院が近くにあれ ば、機能分担もしやすいでしょうが、医療機関が限られている地 域では、ある程度の基準の幅が必要だと思います。また、平均在 院日数を4日も短縮しようとしています。当院は中小病院として 比較的在院日数を短くしていますが、それでもさらに4日短縮す ることは、高齢患者にとって退院後の在宅環境が整わないうちに 退院しなければならないことを意味します。このように、看護必 要度の基準が変更されることで急性期医療に大きな影響が出て、 地域間の医療格差が広がる可能性があります。これらはいずれも、 医療費削減が最終的な目的のようですが、医療費削減にはもっと 無駄な医療に焦点を当てるべきだと考えます。私の意見を述べま したが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。医療は、患者さ んがどのような医療を求めているかによって決めるべきだと思い ます。
令和6年5月